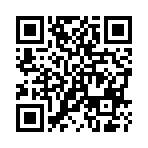2008年09月29日
コンクリートはプリンと同じ?
S邸。

枠を立てて、

コンクリートの打設が終わりました。

これがバケットです。

プロペラは、こうなります。
ところで、このコンクリート。
皆さんの身近にもあると思いますが、
なかなか固まる前の状態をさわる機会はないですよね?
固まる前のコンクリートはフレッシュコンクリート、
日本語で、「生コン」と呼びます。
さらに、
工場で作り、ミキサー車で運ばれてくるものをレディミクストコンクリート、
建設現場で生産するものを現場練りコンクリートと言います。
コンクリートとヒトコトに言っても、かなり種類が多く、奥も深いんです。
現場で使用するときには、固まったあとに想定される「呼び強度」と、
打設作業のしやすさを示す「スランプ値」を指定します。
あと、量も。
コンクリートはセメント、砂、砂利、水、を混ぜて作られていますが、
材料のセメントと水が、化学反応を起こすことで固まります。
水分が抜けて固まるのではないんですね~。
つまり、卵が熱で固まる性質を利用した、
プリンに近いんですよ~。
もちろんコチコチですけど。

枠を立てて、

コンクリートの打設が終わりました。

これがバケットです。

プロペラは、こうなります。
ところで、このコンクリート。
皆さんの身近にもあると思いますが、
なかなか固まる前の状態をさわる機会はないですよね?
固まる前のコンクリートはフレッシュコンクリート、
日本語で、「生コン」と呼びます。
さらに、
工場で作り、ミキサー車で運ばれてくるものをレディミクストコンクリート、
建設現場で生産するものを現場練りコンクリートと言います。
コンクリートとヒトコトに言っても、かなり種類が多く、奥も深いんです。
現場で使用するときには、固まったあとに想定される「呼び強度」と、
打設作業のしやすさを示す「スランプ値」を指定します。
あと、量も。
コンクリートはセメント、砂、砂利、水、を混ぜて作られていますが、
材料のセメントと水が、化学反応を起こすことで固まります。
水分が抜けて固まるのではないんですね~。
つまり、卵が熱で固まる性質を利用した、
プリンに近いんですよ~。
もちろんコチコチですけど。
2008年09月25日
黄色いプロペラは何?
昨日打設したコンクリートも程よく固まり、
S邸の現場は次の準備。

計画された基礎の幅に合わせて、
内側の枠を立てる線を描きます。
「墨出し」といいます。
現場に実物大の図面を書いているようですね~。
もうひとつ。

鉄筋に、無数に取付けられた黄色いプロペラ。
「レベルポインタ」といいます。
立ち上がりのコンクリートを打設するときに
この高さを基準にして、仕上げていきます。
高さ、揃ってるでしょ?

今日の作業は、水平と垂直の基準を出す準備でした~。
次は、枠を立てていきます。
お楽しみに~。
S邸の現場は次の準備。

計画された基礎の幅に合わせて、
内側の枠を立てる線を描きます。
「墨出し」といいます。
現場に実物大の図面を書いているようですね~。
もうひとつ。

鉄筋に、無数に取付けられた黄色いプロペラ。
「レベルポインタ」といいます。
立ち上がりのコンクリートを打設するときに
この高さを基準にして、仕上げていきます。
高さ、揃ってるでしょ?

今日の作業は、水平と垂直の基準を出す準備でした~。
次は、枠を立てていきます。
お楽しみに~。
2008年09月24日
クレーンとミキサー車
祝日でしたが、S邸の現場は作業が進んでいます。
現場には朝から、クレーンとミキサー車が。

でかい。敷地に入りきれてません。
広い道沿いでよかった。通行車両の誘導もスムーズです。
基礎のコンクリート打設です。
今回採用した基礎の形式は「ベタ基礎」。
ベタ基礎は家の形いっぱいに厚いコンクリートの床を作り、
その上に土台が載る立ち上がりを打ちます。
つまり、2回に分けてコンクリートを打つことになります。
今日はその1回目。

クレーンで「バケット」と呼ぶ入れ物を吊り下げ、
その中にミキサー車がコンクリートを流し入れます。
そのまま打設箇所まで吊り動かして、バケットの下を開き、
「ザザ~ッ」と配筋された現場に流し込みます。
それを均して、表面を平らに仕上げます。
なかなかの大作業。
それでも、お昼前には終わりました。
雨が降らなくて、よかった。
現場には朝から、クレーンとミキサー車が。

でかい。敷地に入りきれてません。
広い道沿いでよかった。通行車両の誘導もスムーズです。
基礎のコンクリート打設です。
今回採用した基礎の形式は「ベタ基礎」。
ベタ基礎は家の形いっぱいに厚いコンクリートの床を作り、
その上に土台が載る立ち上がりを打ちます。
つまり、2回に分けてコンクリートを打つことになります。
今日はその1回目。

クレーンで「バケット」と呼ぶ入れ物を吊り下げ、
その中にミキサー車がコンクリートを流し入れます。
そのまま打設箇所まで吊り動かして、バケットの下を開き、
「ザザ~ッ」と配筋された現場に流し込みます。
それを均して、表面を平らに仕上げます。
なかなかの大作業。
それでも、お昼前には終わりました。
雨が降らなくて、よかった。
2008年09月22日
配筋検査

週末のうちに、S邸の配筋が終わりました。
配筋とは、鉄筋を組むこと。
このあと枠を立ててコンクリートを打設するので、鉄筋が隠れてしまう前に検査をして、きちんと設計通りに入っているか、設計事務所と検査機関に確認をしてもらいます。
事前に私がチェックはしているのですが、ここで間違いがあれば手直しです。
ドキドキしますね。
2008年09月18日
トコボリ~捨てコン。
S様邸の基礎工事が、本格的に始まりました。
まずは

1.床堀(トコボリ)。
現場の基準となる高さから、図面で計算した深さまでショベルカーで土を掘ります。
掘った土、4トンダンプ3台分は搬出。

2.砕石を敷き込んで、転圧。
転圧とは、「プレート」や「ランマー」という上下に振動する機械を使って、
砂利を締め固める作業です。
3.シロアリ防蟻処理材の土壌散布。
木材だけでなく、基礎の下や基礎付近の土にもシロアリの予防工事をするんですよ~。
その後、
4.防湿のためのポリフイルムを敷き込んで、
5.外周周りに捨てコンの打設です。
この捨てコンは外枠の線を直接書いて、その線に沿って外枠を並べるためのものです。
ここまで、昨日丸一日の作業。
台風も近づいているので、できるところまでは大急ぎで。
職人さん方、お疲れさまです。
午後はカメラも携帯も会社に忘れ、
様子が伝えられず、無念です。。

この間、会社では外観イメージの確認と、サッシの確認を行っています。
次々と進めていかなくては。。
まずは

1.床堀(トコボリ)。
現場の基準となる高さから、図面で計算した深さまでショベルカーで土を掘ります。
掘った土、4トンダンプ3台分は搬出。

2.砕石を敷き込んで、転圧。
転圧とは、「プレート」や「ランマー」という上下に振動する機械を使って、
砂利を締め固める作業です。
3.シロアリ防蟻処理材の土壌散布。
木材だけでなく、基礎の下や基礎付近の土にもシロアリの予防工事をするんですよ~。
その後、
4.防湿のためのポリフイルムを敷き込んで、
5.外周周りに捨てコンの打設です。
この捨てコンは外枠の線を直接書いて、その線に沿って外枠を並べるためのものです。
ここまで、昨日丸一日の作業。
台風も近づいているので、できるところまでは大急ぎで。
職人さん方、お疲れさまです。
午後はカメラも携帯も会社に忘れ、
様子が伝えられず、無念です。。

この間、会社では外観イメージの確認と、サッシの確認を行っています。
次々と進めていかなくては。。