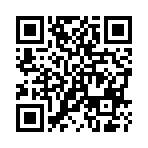2009年01月14日
木のアクセント
先日のコメントにあった、まーちんさんの質問にお答えします。。。
S邸の外観のアクセントとなっているのが、
茶色のパネル。今は4枚ですね~。
もう少し増える予定ですが。

これは、雨戸を収納する戸袋(とぶくろ)です。
通常は飾りのパネルが入ります。
これを「鏡板(かがみいた)」と呼びますが。


この鏡板を、杉板にしてみました。
軒天と同じ、キシラデコールのオリーブ色で着色しています。
キシラデコールには、防虫防腐の作用があります。
当然、中に納まる雨戸本体の動きには問題ないように
考えながら下地もいれています。
思った以上にすっきりと納まり、ニヤニヤもんです~。
S邸の外観のアクセントとなっているのが、
茶色のパネル。今は4枚ですね~。
もう少し増える予定ですが。

これは、雨戸を収納する戸袋(とぶくろ)です。
通常は飾りのパネルが入ります。
これを「鏡板(かがみいた)」と呼びますが。


この鏡板を、杉板にしてみました。
軒天と同じ、キシラデコールのオリーブ色で着色しています。
キシラデコールには、防虫防腐の作用があります。
当然、中に納まる雨戸本体の動きには問題ないように
考えながら下地もいれています。
思った以上にすっきりと納まり、ニヤニヤもんです~。
2009年01月09日
この樋、変わってる~
S邸の雨樋は、ちょっと変わってるんです。
何が違うか、分かりますか?

まずこの樋、半丸という形です。
他には角樋という,断面が四角い形があります。
よく使うのは樹脂製ですが、
これはガルバルウム鋼板製です。
この写真は、なんかすっきりしてるでしょ?
1階屋根の正面側は呼び樋をつけていません。
呼び樋とは、庇の先から壁までの斜めに引き寄せる部分のことですが、
この部分は庇が出ていないので、こういう形になりました。。
さらにあんこうと呼んでいる、軒樋から竪樋に落とし込む部分。
ラッパのように拡がって、つながっています。
通常は大きな四角いハコのようなものが付いています。

そしてマルは通常は下から支える形ですが、
この樋は上吊式になっています。
下から腕が見えないようになっています。
角樋ならばあんこうもなく、ほとんどが上吊式なのですが、
丸樋ではめずらしいんです。

こんな小さな工夫を、S邸ではコマゴマと取り込んでいます~。
何が違うか、分かりますか?

まずこの樋、半丸という形です。
他には角樋という,断面が四角い形があります。
よく使うのは樹脂製ですが、
これはガルバルウム鋼板製です。
この写真は、なんかすっきりしてるでしょ?
1階屋根の正面側は呼び樋をつけていません。
呼び樋とは、庇の先から壁までの斜めに引き寄せる部分のことですが、
この部分は庇が出ていないので、こういう形になりました。。
さらにあんこうと呼んでいる、軒樋から竪樋に落とし込む部分。
ラッパのように拡がって、つながっています。
通常は大きな四角いハコのようなものが付いています。

そしてマルは通常は下から支える形ですが、
この樋は上吊式になっています。
下から腕が見えないようになっています。
角樋ならばあんこうもなく、ほとんどが上吊式なのですが、
丸樋ではめずらしいんです。

こんな小さな工夫を、S邸ではコマゴマと取り込んでいます~。
2009年01月08日
白壁の秘密(後編)
この白壁の秘密、後編です。

いよいよ仕上げ塗りです。
実はこの白壁、平らではないんです。
アップで見ると、


くし引き仕上げになっています。
材料はエスケー化研のベルアートSi。
塗るのは三代に渡ってお世話になっている、こざき塗装さんです。
この仕上げのよい!と思うところは
・横ラインが、シャープかつシンプル~。
・継ぎ手やダマに職人さんの手作業の跡があり、面白い。
・小さな山々の小さな影が落ちるので、白く見えすぎない。
などなど。
逆に雨による汚れは目立ちやすそうだし、
職人さんのパターンに?と思うところもありました。
それらは汚れにくい材料を選んだり、
チェックして数十箇所の手直しをしてもらったりして、
少しでも軽減できるようにしています。

いよいよ仕上げ塗りです。
実はこの白壁、平らではないんです。
アップで見ると、


くし引き仕上げになっています。
材料はエスケー化研のベルアートSi。
塗るのは三代に渡ってお世話になっている、こざき塗装さんです。
この仕上げのよい!と思うところは
・横ラインが、シャープかつシンプル~。
・継ぎ手やダマに職人さんの手作業の跡があり、面白い。
・小さな山々の小さな影が落ちるので、白く見えすぎない。
などなど。
逆に雨による汚れは目立ちやすそうだし、
職人さんのパターンに?と思うところもありました。
それらは汚れにくい材料を選んだり、
チェックして数十箇所の手直しをしてもらったりして、
少しでも軽減できるようにしています。
2009年01月07日
白壁の秘密(前編)
この美しい白壁には、秘密があるのです~。
日にちを遡って、その過程を追います。
塗装前の状態はこちら。

平坦にするために、目地を左官塗りでつぶしています。
これに塗装開始。。
とは言っても、まずは下塗りから。
サイディングと目地を埋めた部分では塗料の吸い込み具合が違うため、そのまま仕上げ材を塗ってしまうと仕上がりが違ってしまう可能性があります。
そこで活躍するのが、シーラーと呼ばれる下塗り材。
塗料を吸い込みにくくし、均一な仕上がりに近づけます。

お化粧で言えば、ファンデーション、かな?

これで一日、乾燥です。
続きは、また明日。
いよいよ仕上げ塗り。秘密が明らかに!
日にちを遡って、その過程を追います。
塗装前の状態はこちら。

平坦にするために、目地を左官塗りでつぶしています。
これに塗装開始。。
とは言っても、まずは下塗りから。
サイディングと目地を埋めた部分では塗料の吸い込み具合が違うため、そのまま仕上げ材を塗ってしまうと仕上がりが違ってしまう可能性があります。
そこで活躍するのが、シーラーと呼ばれる下塗り材。
塗料を吸い込みにくくし、均一な仕上がりに近づけます。

お化粧で言えば、ファンデーション、かな?

これで一日、乾燥です。
続きは、また明日。
いよいよ仕上げ塗り。秘密が明らかに!
2009年01月06日
外観現る。。。
年末の12月27日、外部の足場を外しました。
寒い中、職人さんがどんどん解体していきます。


そして現れたのが、この外観。


木部が白い壁に映えて、綺麗な外観が現れました。
自分で言うのもなんですが、満足のできばえです!
寒い中、職人さんがどんどん解体していきます。


そして現れたのが、この外観。


木部が白い壁に映えて、綺麗な外観が現れました。
自分で言うのもなんですが、満足のできばえです!
2008年11月21日
実は屋根のスキマも。。。
重要なんです。屋根のスキマも。
同じく通気工法です。
↓板を張る前ですが、この部分がスキマです。

2階の屋根は片方だけに傾いている、片流れ(かたながれ)という形式です。
その一番上と

一番下の列。

そこに軒先通気部材を取付けています。
細かい穴がたくさん開いていて、
一番下が空気を吸い込み、一番上から放出。
濃い色の板金屋根で特に熱されやすいので、必要な機能です。
S邸の軒裏は、杉板を張っています。
この杉材と近い色で、見た目も気になりません~。

寒くなってきました。
体調管理にも気をつけて、がんばろう!
ワタクシゴトで恐縮ですが、
来週の水曜日(26日)、熊日の夕刊を見てみてください。
インタビュー「あなたを聞かせて」の欄で、
人物紹介でど~んと一面、私みやもとを紹介されるそうです。
町屋の話、まちづくりの話、仕事の話、すべての記事が出ると思います。
こちらもお楽しみに~。
同じく通気工法です。
↓板を張る前ですが、この部分がスキマです。

2階の屋根は片方だけに傾いている、片流れ(かたながれ)という形式です。
その一番上と

一番下の列。

そこに軒先通気部材を取付けています。
細かい穴がたくさん開いていて、
一番下が空気を吸い込み、一番上から放出。
濃い色の板金屋根で特に熱されやすいので、必要な機能です。
S邸の軒裏は、杉板を張っています。
この杉材と近い色で、見た目も気になりません~。

寒くなってきました。
体調管理にも気をつけて、がんばろう!
ワタクシゴトで恐縮ですが、
来週の水曜日(26日)、熊日の夕刊を見てみてください。
インタビュー「あなたを聞かせて」の欄で、
人物紹介でど~んと一面、私みやもとを紹介されるそうです。
町屋の話、まちづくりの話、仕事の話、すべての記事が出ると思います。
こちらもお楽しみに~。
2008年11月20日
紙と壁のスキマが重要!
外壁工事もどんどん進んでいます。
まず、透湿防水紙に木材を等間隔に打ち付けます。

これを胴縁(どうぶち)と呼びます。
この上にサイディングというセメント板を張るのですが、
防水紙とサイディングの間の隙間が、実は建物を守るんです。
何から守るのか…それは熱から。
胴縁には、わざと間隔が設けてあります。

大工さんが雑に工事したわけではないんですよ~。
この隙間から、熱せられた空気が上に逃げていくんです。
空気は天井裏を通って、屋根の先から外に抜けていきます。
つまり、壁の熱気が自然と外に出て行く工法。
これを、外壁通気工法と呼びます。
セメント板を張り進めるS邸は、こんな感じ。

でも、まだまだ仕上げではありません。
お楽しみに~。

まず、透湿防水紙に木材を等間隔に打ち付けます。

これを胴縁(どうぶち)と呼びます。
この上にサイディングというセメント板を張るのですが、
防水紙とサイディングの間の隙間が、実は建物を守るんです。
何から守るのか…それは熱から。
胴縁には、わざと間隔が設けてあります。

大工さんが雑に工事したわけではないんですよ~。
この隙間から、熱せられた空気が上に逃げていくんです。
空気は天井裏を通って、屋根の先から外に抜けていきます。
つまり、壁の熱気が自然と外に出て行く工法。
これを、外壁通気工法と呼びます。
セメント板を張り進めるS邸は、こんな感じ。

でも、まだまだ仕上げではありません。
お楽しみに~。

2008年10月25日
紙のイエ
S邸が、紙の家になりました。
白い紙で、窓以外の外部を覆ってしまったところです。

実はこの紙、ただの紙ではありません。
「透湿防水シート」。
文字通り、内側の湿気は通すが外側の水は通さないという、
水にとっては一方通行の紙なんです。
その性質を利用して、外部からの雨の浸入を防ぎつつ、
壁の内部の空気が含む余分な湿気を、外に放出してくれます。
これで、壁内部の温度変化による結露を抑えることができます。
それより何より、外から筒抜けだった建物に、中と外の区切りができました。
家らしくなってきましたね~。
白い紙で、窓以外の外部を覆ってしまったところです。

実はこの紙、ただの紙ではありません。
「透湿防水シート」。
文字通り、内側の湿気は通すが外側の水は通さないという、
水にとっては一方通行の紙なんです。
その性質を利用して、外部からの雨の浸入を防ぎつつ、
壁の内部の空気が含む余分な湿気を、外に放出してくれます。
これで、壁内部の温度変化による結露を抑えることができます。
それより何より、外から筒抜けだった建物に、中と外の区切りができました。
家らしくなってきましたね~。
2008年10月20日
軽い屋根。
屋根を葺く材料には、いくつかの種類があります。
一番多いのはおなじみの瓦葺き。
ほかにも茅葺、トタン、レンガ、スレート、コンクリートなどがありますが、
今回S邸で使用したのは、「塗装ガルバリウム鋼板」葺き。
「ガルバリウム」は正確には、
「溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板」と呼びます。
ステンレスに次ぐ高い防食性を生かして、建物の外壁や屋根の材料に良く使われています。
くすんだシルバーの金属で作られた外壁のモダンな建物、皆さんの周りにもありませんか~?
このガルバリウムに屋外使用向け塗装が施された屋根材は、より高度な防食性を持っています。
今回のS邸では、この中で瓦に近い色が選ばれました。

この葺き方は、クリップパネル工法といいます。
継ぎ目のない一枚板で水上から水下まで葺くので、
腐食して穴が開かない限り、雨漏りの心配はほとんどありません。

また、金属屋根は熱しやすい分冷めやすいので、真夏の夜でも熱がこもりにくい性質もあります。
Sさん一家を雨や日差しから守る、重要な役割を担います。

一番多いのはおなじみの瓦葺き。
ほかにも茅葺、トタン、レンガ、スレート、コンクリートなどがありますが、
今回S邸で使用したのは、「塗装ガルバリウム鋼板」葺き。
「ガルバリウム」は正確には、
「溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板」と呼びます。
ステンレスに次ぐ高い防食性を生かして、建物の外壁や屋根の材料に良く使われています。
くすんだシルバーの金属で作られた外壁のモダンな建物、皆さんの周りにもありませんか~?
このガルバリウムに屋外使用向け塗装が施された屋根材は、より高度な防食性を持っています。
今回のS邸では、この中で瓦に近い色が選ばれました。

この葺き方は、クリップパネル工法といいます。
継ぎ目のない一枚板で水上から水下まで葺くので、
腐食して穴が開かない限り、雨漏りの心配はほとんどありません。

また、金属屋根は熱しやすい分冷めやすいので、真夏の夜でも熱がこもりにくい性質もあります。
Sさん一家を雨や日差しから守る、重要な役割を担います。