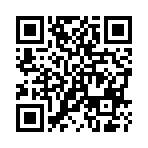2009年02月16日
手作りの手摺。
S邸の階段を2階に上がると、平行して廊下があります。
その廊下と階段の境の手摺のお話。
ちなみに、去年新築したW邸の手摺はこちら。
この場合には、
・壁を立ち上げてクロスを張り、天板をつける
・手摺子と親柱で、縦横の格子状に組む
などの方法がありますが、
広く見せるために格子状の手摺になりました。
既製品をいくつか見たのですが、
強度を満たし、かつデザインのよいものがないので、
大工さんに作ってもらうことにしました。
まずは図面を書いて、

分かりやすく3Dも作ってみました。

大工さんと少しでも強い収まりも検討し、

そしてできたものがこちら。

階段から見上げると、

集成材とはいえ、力量を発揮できた大工さんも満足げでした。
当然ですが、職人も含め、自分達が納得できるものを
納めるようにしています。
その廊下と階段の境の手摺のお話。
ちなみに、去年新築したW邸の手摺はこちら。
この場合には、
・壁を立ち上げてクロスを張り、天板をつける
・手摺子と親柱で、縦横の格子状に組む
などの方法がありますが、
広く見せるために格子状の手摺になりました。
既製品をいくつか見たのですが、
強度を満たし、かつデザインのよいものがないので、
大工さんに作ってもらうことにしました。
まずは図面を書いて、

分かりやすく3Dも作ってみました。

大工さんと少しでも強い収まりも検討し、

そしてできたものがこちら。

階段から見上げると、

集成材とはいえ、力量を発揮できた大工さんも満足げでした。
当然ですが、職人も含め、自分達が納得できるものを
納めるようにしています。
2008年12月19日
床と壁のあいだ
みなさんの今いる部屋は、壁と床の間、どうなってますか?
大抵のばあい、壁に5センチ~10センチの板が貼ってあると思います。
これを巾木(はばき)と言います。
S邸では、床の仕上げに合わせてこの巾木も変えています。
既製品のフローリングの床には、同色の巾木。


杉板の床には、杉の無垢材の巾木。
シート貼りの床は、白い巾木で壁のクロスに合わせて。
周り階段の部分にも、段に合わせて巾木を張ります。

みなさんの今いる部屋は、壁と床の間、どうなってますか?
大抵のばあい、壁に5センチ~10センチの板が貼ってあると思います。
これを巾木(はばき)と言います。
S邸では、床の仕上げに合わせてこの巾木も変えています。
既製品のフローリングの床には、同色の巾木。


杉板の床には、杉の無垢材の巾木。
シート貼りの床は、白い巾木で壁のクロスに合わせて。
周り階段の部分にも、段に合わせて巾木を張ります。

みなさんの今いる部屋は、壁と床の間、どうなってますか?
2008年12月09日
階段って、こうなってる
とは言っても、いろいろあるんですけど。。。
今日はS邸の、側桁式箱階段。
S邸の階段は、
下から3段が回り階段、直階段8段、
一番上にまた回り階段が3段あります。
左右を壁に挟まれている部分を「箱階段」といいます。
回り階段の螺旋の中心は、大工さんが柱を切り欠いて差し込みます。

螺旋の外側には、それぞれ壁の下地に踏板の受け材が入っています。
階段の下が見えないように塞ぐ板を蹴込板(けこみいた)と言います。

直線部分は左右の壁に溝を掘った側板を固定し、
その溝に踏み板を差し込みます。
このとき、蹴込板も一緒に踏板に差し込みます。
壁を張ってしまうとなかなか見られない、階段の骨組み。

階段下は、収納になる予定です。
今日はS邸の、側桁式箱階段。
S邸の階段は、
下から3段が回り階段、直階段8段、
一番上にまた回り階段が3段あります。
左右を壁に挟まれている部分を「箱階段」といいます。
回り階段の螺旋の中心は、大工さんが柱を切り欠いて差し込みます。

螺旋の外側には、それぞれ壁の下地に踏板の受け材が入っています。
階段の下が見えないように塞ぐ板を蹴込板(けこみいた)と言います。

直線部分は左右の壁に溝を掘った側板を固定し、
その溝に踏み板を差し込みます。
このとき、蹴込板も一緒に踏板に差し込みます。
壁を張ってしまうとなかなか見られない、階段の骨組み。

階段下は、収納になる予定です。
2008年12月05日
少しずつ
S邸も内部の様子が変わってきました。
骨組みとなる下地を組んで。

オープンキッチンの裏の収納カウンターも、ようやく姿を見せ始めました。

石膏ボードがどんどん張られていきます。

建具の枠。これが手間かかってるんです。
既製品でなく手作りなので。

2階の子供部屋。

いろいろご紹介したいのですが、細かいところはまた後日。
骨組みとなる下地を組んで。

オープンキッチンの裏の収納カウンターも、ようやく姿を見せ始めました。

石膏ボードがどんどん張られていきます。

建具の枠。これが手間かかってるんです。
既製品でなく手作りなので。

2階の子供部屋。

いろいろご紹介したいのですが、細かいところはまた後日。
2008年11月20日
天井ボード
先日の天井下地組みの上に、ボードが貼られました。

石膏ボード、9.5ミリ。
↓これが張る前。

今回、建具の高さが天井まである部分があります。
そこは当然、枠も天井まで。

だんだん、部屋の形が見えてきました。

石膏ボード、9.5ミリ。
↓これが張る前。

今回、建具の高さが天井まである部分があります。
そこは当然、枠も天井まで。

だんだん、部屋の形が見えてきました。
2008年11月13日
天井裏と壁のなか
床を張って、ようやく安心して歩けるようになったS邸の1階。
早速足場が組まれ、天井の工事です。

大工さんが、天井の下地を組みあげました。
このあと天井にはボードを張ります。
天井もすごいですが、現場の余り材を使用した足場もすごいです。
同時に、電気設備と給排水設備の準備も進みます。
これは、トイレの天井の換気扇。
天井裏を通って、外壁面へダクトが伸びています。

テレビ、LANの集中中継スペースには無数の配管、配線が。

手前に立ち上がっているパイプは、2階からトイレの汚水が流れてきます。洗濯機の裏にうま~く隠れる予定。

これらは仕上がってしまうと見えなくなりますが、繋がっていないと大変なことになります。
しっかりお願いしますよ!リュウ設備さん、谷崎電気さん!
早速足場が組まれ、天井の工事です。

大工さんが、天井の下地を組みあげました。
このあと天井にはボードを張ります。
天井もすごいですが、現場の余り材を使用した足場もすごいです。
同時に、電気設備と給排水設備の準備も進みます。
これは、トイレの天井の換気扇。
天井裏を通って、外壁面へダクトが伸びています。

テレビ、LANの集中中継スペースには無数の配管、配線が。

手前に立ち上がっているパイプは、2階からトイレの汚水が流れてきます。洗濯機の裏にうま~く隠れる予定。

これらは仕上がってしまうと見えなくなりますが、繋がっていないと大変なことになります。
しっかりお願いしますよ!リュウ設備さん、谷崎電気さん!
2008年11月10日
杉40厚板の床、イイ!
先日加工した枠を納めたところから、1階の床張りが始まりました。
1階のメインとなるのは、この杉の床材です。

厚さ、なんと4センチ!
普通のフローリングは下地を合わせても2.4センチしかありません。
この材料は、森林認証を取り産直住宅を推進されている、宮崎県の諸塚村から取り寄せています。
構造的な迫力と柔らかな手触りを持っていて、これまでも何度か使わせてもらっています。
断熱性能も高く、実際に、直接座っても暖かいです!
枠に合わせて、ぴったりに切ります。

仕上がりがそのまま見えてくるので、大工さんもごまかしが効きません。
そんな手間のかかる仕事を楽しんでするのが、武永大工のすごいところ。


出来上がりが楽しみですが、この床は特にやわらかく傷が入りやすいので、すぐに養生です。
後は全工事が完成するまで、見ることはできません。
完成が待ち遠しいです。
1階のメインとなるのは、この杉の床材です。

厚さ、なんと4センチ!
普通のフローリングは下地を合わせても2.4センチしかありません。
この材料は、森林認証を取り産直住宅を推進されている、宮崎県の諸塚村から取り寄せています。
構造的な迫力と柔らかな手触りを持っていて、これまでも何度か使わせてもらっています。
断熱性能も高く、実際に、直接座っても暖かいです!
枠に合わせて、ぴったりに切ります。

仕上がりがそのまま見えてくるので、大工さんもごまかしが効きません。
そんな手間のかかる仕事を楽しんでするのが、武永大工のすごいところ。


出来上がりが楽しみですが、この床は特にやわらかく傷が入りやすいので、すぐに養生です。
後は全工事が完成するまで、見ることはできません。
完成が待ち遠しいです。
2008年11月06日
枠、加工
雨の合間を縫って、大工さんが建具の枠の加工を始めました。

枠の太さは、通常の既製品なら20ミリ~24ミリ程度。
和室などでは40ミリなどになることもありますが、
S邸では、15ミリ。
普通、15ミリでは細すぎて、開け閉めの衝撃に耐えられません。
ひと手間かけて、15ミリに見えるように、

両端だけ細くしています。
ゲンブツの写真を撮り忘れました~。
加工の成果はまた後日…。

枠の太さは、通常の既製品なら20ミリ~24ミリ程度。
和室などでは40ミリなどになることもありますが、
S邸では、15ミリ。
普通、15ミリでは細すぎて、開け閉めの衝撃に耐えられません。
ひと手間かけて、15ミリに見えるように、

両端だけ細くしています。
ゲンブツの写真を撮り忘れました~。
加工の成果はまた後日…。
2008年11月05日
建具検討…ドア?引戸?
皆さんのお家、部屋と部屋との間の建具は「何」ですか?
襖(ふすま)や障子(しょうじ)も含めて、
建具の材質にもいろいろありますが、
ここでは開き方について。
一番多いのは、開き戸だと思います。
いわゆる「ドア」。
ドアノブかレバーハンドルを回して、蝶板(ちょうばん)を軸に90度かそれ以上開く形式ですね。
次に多いのは、和の建具の基本である引戸(ひきど)。
建具が1枚で、壁に沿って開いてしまうものを引込み戸(ひきこみど)、
建具が2枚かそれ以上で、両側を開くことができるものを引違い戸(ひきちがいど)と言います。
他にも、クローゼットに使われる折れ戸(おれど)などがありますね。
これらの建具、最近ではほとんど既製品を使うことが多いのですが、S邸ではすべて製作することになっています。
建具だけでなく、開き方にあわせて枠(わく)も製作です。
実は建具本体よりも、壁に取りつける枠が大変。
今日は、大工さんとこの枠の打合せです。
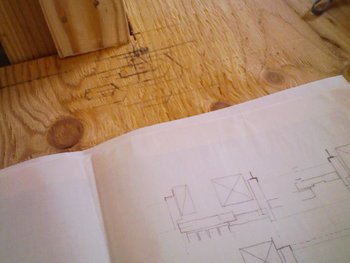
私が描いた図面を元に、現場に実際に書き写してみて、うまくいくかどうかを検討します。
それも、ほとんどの箇所で納まりが変わってくる、このS邸。
結構、苦戦中です。
襖(ふすま)や障子(しょうじ)も含めて、
建具の材質にもいろいろありますが、
ここでは開き方について。
一番多いのは、開き戸だと思います。
いわゆる「ドア」。
ドアノブかレバーハンドルを回して、蝶板(ちょうばん)を軸に90度かそれ以上開く形式ですね。
次に多いのは、和の建具の基本である引戸(ひきど)。
建具が1枚で、壁に沿って開いてしまうものを引込み戸(ひきこみど)、
建具が2枚かそれ以上で、両側を開くことができるものを引違い戸(ひきちがいど)と言います。
他にも、クローゼットに使われる折れ戸(おれど)などがありますね。
これらの建具、最近ではほとんど既製品を使うことが多いのですが、S邸ではすべて製作することになっています。
建具だけでなく、開き方にあわせて枠(わく)も製作です。
実は建具本体よりも、壁に取りつける枠が大変。
今日は、大工さんとこの枠の打合せです。
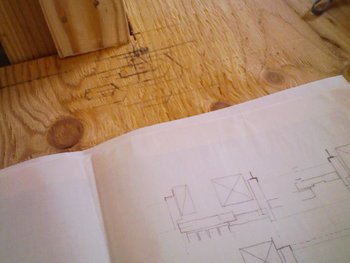
私が描いた図面を元に、現場に実際に書き写してみて、うまくいくかどうかを検討します。
それも、ほとんどの箇所で納まりが変わってくる、このS邸。
結構、苦戦中です。
2008年11月04日
床の色
S邸の室内の床は、大きく3種類の材料で張られます。
そのうちの一種、2階のフローリング工事に入りました。
フローリングの色は、今回2種類。
廊下、子供部屋に選ばれた自然なバーチ色と、

親寝室に選ばれた、シックなダークセピア色です。

すでに全面にベニヤ板を敷いて、見えなくなってますが。
このベニヤの下には。さらに一枚耐水シートを敷いています。

このベニヤ板がこれから壁と天井の工事の作業があるので、物を落したり脚立を置いたりしたときに床に傷が入らないように守っているのです。
これを養生(ようじょう)といいます。
そのうちの一種、2階のフローリング工事に入りました。
フローリングの色は、今回2種類。
廊下、子供部屋に選ばれた自然なバーチ色と、

親寝室に選ばれた、シックなダークセピア色です。

すでに全面にベニヤ板を敷いて、見えなくなってますが。
このベニヤの下には。さらに一枚耐水シートを敷いています。

このベニヤ板がこれから壁と天井の工事の作業があるので、物を落したり脚立を置いたりしたときに床に傷が入らないように守っているのです。
これを養生(ようじょう)といいます。