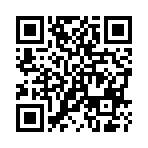2008年11月10日
テレビ出演
先日のテレビタミンでの画像です。
会社のちっちゃいテレビで、みんなで見てました。
安全第一、宮本建設。
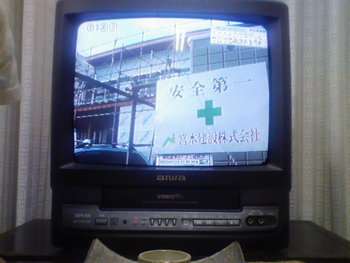
当社の謳い文句はこれしかありません。
お客さま第一、よりも大事です。
そして、インタビューです。

「飲み会も含め、地域、業種を越えてブログ上で商店間のコミュニケーションが取れるのが楽しい」
と申してました。
なんか、よっぽど飲みたい人みたいですね。
そして、かすみそうさん。

「ブログを見られた方の反響は大きい」
と言われていたような。
他にも出られていた方々、撮りきれませんでした。
すみません~。
会社のちっちゃいテレビで、みんなで見てました。
安全第一、宮本建設。
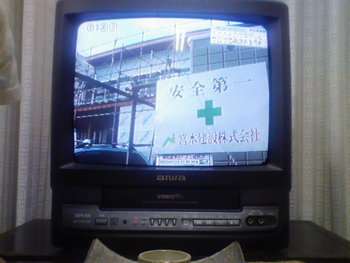
当社の謳い文句はこれしかありません。
お客さま第一、よりも大事です。
そして、インタビューです。

「飲み会も含め、地域、業種を越えてブログ上で商店間のコミュニケーションが取れるのが楽しい」
と申してました。
なんか、よっぽど飲みたい人みたいですね。
そして、かすみそうさん。

「ブログを見られた方の反響は大きい」
と言われていたような。
他にも出られていた方々、撮りきれませんでした。
すみません~。
2008年10月29日
ガラスの羊毛。
ガラスの羊毛。グラスウール。
ガラスの繊維でできた素材で、外壁面の断熱材として使用します。
現場に搬入されるときは、こんなウインナーみたいな梱包。

空気を抜いて圧縮されているので、一度開けると一気に膨らみます。

この空気層が、セーターのように建物を包み込みます。
梱包を解いても、グラスウール自体はまだ薄いビニールに包まれているのですが、木造の一般的な寸法に梱包されているので、ホッチキスのようなタッカーという道具で、このまま壁に留めていきます。
この梱包のビニールによって、建物の中に余計な湿気を入れないという、よくできた製品。

壁だけでなく屋根に面した天井にも、このグラスウールを敷き込んでいきます。
ガラスの繊維でできた素材で、外壁面の断熱材として使用します。
現場に搬入されるときは、こんなウインナーみたいな梱包。

空気を抜いて圧縮されているので、一度開けると一気に膨らみます。

この空気層が、セーターのように建物を包み込みます。
梱包を解いても、グラスウール自体はまだ薄いビニールに包まれているのですが、木造の一般的な寸法に梱包されているので、ホッチキスのようなタッカーという道具で、このまま壁に留めていきます。
この梱包のビニールによって、建物の中に余計な湿気を入れないという、よくできた製品。

壁だけでなく屋根に面した天井にも、このグラスウールを敷き込んでいきます。
2008年10月23日
窓とドア。
S邸の現場に、シルバーの枠が付けられていきます。
もちろん、アルミサッシの窓枠です。

よく見ると分かりますが、
まだ肝心のガラス窓自体は届いていないところもあります。
壁もないので、まだスカスカですね。
このアルミサッシ、昔はほとんどシルバーしかありませんでした。
アルミ本来の色です。
しかし製作技術が進むにつれ、ブロンズ色や白、黒、濃茶色などが多くなり、
近年ではステンレスを模したシャンパンゴールドのような「ステンカラー」まで出回って、
一時、味気ない雰囲気のシルバーのサッシは販売されていませんでした。
しかし、この「味気なさ」がまた見直されて、TOSTEMでは「ナチュラルシルバー色」として復活しました。
S邸には、この「ナチュラルシルバー色」を使用しています。
建築の材料、色にも流行があるんですよ~。
ファッションのように、「今年のトレンド色は~」と報道される日も来るかもしれませんね。
もちろん、アルミサッシの窓枠です。

よく見ると分かりますが、
まだ肝心のガラス窓自体は届いていないところもあります。
壁もないので、まだスカスカですね。
このアルミサッシ、昔はほとんどシルバーしかありませんでした。
アルミ本来の色です。
しかし製作技術が進むにつれ、ブロンズ色や白、黒、濃茶色などが多くなり、
近年ではステンレスを模したシャンパンゴールドのような「ステンカラー」まで出回って、
一時、味気ない雰囲気のシルバーのサッシは販売されていませんでした。
しかし、この「味気なさ」がまた見直されて、TOSTEMでは「ナチュラルシルバー色」として復活しました。
S邸には、この「ナチュラルシルバー色」を使用しています。
建築の材料、色にも流行があるんですよ~。
ファッションのように、「今年のトレンド色は~」と報道される日も来るかもしれませんね。
2008年10月14日
骨組みに金物
昔の大工さんたちは、建物を建てるのにほとんど鉄を使いませんでした。
しかし現在では、社寺建築を除いて、そのような建物はほとんどありません。
なぜなら、木造建築の耐震性能を一定以上に保つために、
国土交通省の告示によって金物を使用するように規定されているからです。
もちろんS邸でも、多くの金物が使用されています。
主なものでは、
梁から梁が抜けないようにするための羽子板金物。

土台や梁から柱が抜けないようにするためのL型金物。

地震耐力を持たせるための筋交いが外れないようにする筋交い金物。

基礎から建物、特に柱がずれないようにするホールダウン金物。

などがあります。
地震大国日本ならではの、
安全を守る仕組みです。。
しかし現在では、社寺建築を除いて、そのような建物はほとんどありません。
なぜなら、木造建築の耐震性能を一定以上に保つために、
国土交通省の告示によって金物を使用するように規定されているからです。
もちろんS邸でも、多くの金物が使用されています。
主なものでは、
梁から梁が抜けないようにするための羽子板金物。

土台や梁から柱が抜けないようにするためのL型金物。

地震耐力を持たせるための筋交いが外れないようにする筋交い金物。

基礎から建物、特に柱がずれないようにするホールダウン金物。

などがあります。
地震大国日本ならではの、
安全を守る仕組みです。。
2008年10月07日
モクモクと作業。。
S邸、木工事が進んでいます。

まずは筋交(すじかい)。
柱と梁に囲まれたところに、斜めに木材をはめ込みます。
箱につっかえ棒を入れて、つぶれないようにするのと同じ。
すべて金物でも補強をしたのですが、この話はまた後日。
そして間柱(まばしら)。
文字通り、柱の間に立てて壁を支えます
1階が終わり、お昼からは2階へ。
2階は足場がなく歩けないので、先に床の下地を組みます。

根太(ねだ)を梁(はり)に渡して、ビスで固定。
仮にベニヤ板を敷いて安全に作業ができるようにします。

私は金物の取り付けと、根太のビス止めを担当。
2階の梁の上でヒヤヒヤしながら、汗ダク。。
外から見た目はそう変わりませんが、
大工さんと2人で作業、だいぶはかどりました。
明日もガンバロ~!

まずは筋交(すじかい)。
柱と梁に囲まれたところに、斜めに木材をはめ込みます。
箱につっかえ棒を入れて、つぶれないようにするのと同じ。
すべて金物でも補強をしたのですが、この話はまた後日。
そして間柱(まばしら)。
文字通り、柱の間に立てて壁を支えます
1階が終わり、お昼からは2階へ。
2階は足場がなく歩けないので、先に床の下地を組みます。

根太(ねだ)を梁(はり)に渡して、ビスで固定。
仮にベニヤ板を敷いて安全に作業ができるようにします。

私は金物の取り付けと、根太のビス止めを担当。
2階の梁の上でヒヤヒヤしながら、汗ダク。。
外から見た目はそう変わりませんが、
大工さんと2人で作業、だいぶはかどりました。
明日もガンバロ~!
2008年10月06日
上棟!建ち上がるまで。

お盆開けに始まったS邸の新築工事も、
ひとつの節目を迎えました。
上棟(じょうとう)です。
棟上げ(むねあげ)とも言います。
他にも建て方(たてかた)、建前(たてまえ)など、いくつかの呼び方があります。
今回は二日に渡って、搬入していたプレカット材を組み立てました。
一日目。
基礎の上に基礎パッキンを並べます。
その上に敷く土台とコンクリートの基礎との間に、空気が通う隙間を空けるためのもの。
そして土台(どだい)を敷き込みますが、
このときに、アンカーボルトを通すための穴をひとつひとつ開けます。
微妙にずれているので、調整しながら。

柱を立てます。
縦に「123」、横に「いろは」で碁盤の目状の位置が、
柱の一本一本に印刷してあります。
「を-8」を、そこに持っていき、立てる。

梁(はり)・桁(けた)をかけます。
普通はここからクレーン登場。
しかし4人の大工さんたちはそんなの待っていられません。
脚立とロープで、1階の梁をほとんど掛けてしまいました。
「昔はクレーンなんかなかったっだけん!」
さすがベテランぞろい。
二日目。
クレーン登場。大工さん、なんと8人。
1階の残りの梁をかけ終えると、二階の柱。
そして二階の梁。早い早い。

午後から、2階の垂木(たるき)の取付け。
長さを揃えて切り、破風板(はふいた)、幕板(まくいた)を屋根の周囲にぐるりと打ち付けます。
野地板(のじいた)と呼ぶ、屋根の下地板として合板を張り、金属板屋根なので音と熱の緩衝用にプラスターボードを張りました。
その後、同様に1階の屋根に進みます。
その頃には屋根工事の板金屋さんも到着、終わった2階から防水のためのルーフィングというシートを張り始めます。

何とか終わったのが7時頃、あたりは真っ暗になりました。
屋根裏に飾りとお札をくくり付け、神様に二礼二拍手一礼。
Sさんから、ねぎらいの言葉とお弁当を頂きました。
感無量。
雨も降らず、終わることができた棟上。
監督、と言いながら結構手伝い、私もバタバタ動き回りました。。
家で一人、祝杯。
やっと木工事のスタートです。
2008年10月02日
高いところ
怖いという方、多いのではないですか?
高いところ。
登ってきました。
地上6m。
「たったの6m~?」という声が聞こえてきますが、
こんな感じです。

まあ、実際たいしたことないです。

左端の一番上からの画像です。
新築の際には、先に足場を建てます。
上棟のときの大工さんの安全のために。
当社では、ビケ足場を使用しています。
高いところ。
登ってきました。
地上6m。
「たったの6m~?」という声が聞こえてきますが、
こんな感じです。

まあ、実際たいしたことないです。

左端の一番上からの画像です。
新築の際には、先に足場を建てます。
上棟のときの大工さんの安全のために。
当社では、ビケ足場を使用しています。
2008年10月01日
木材搬入+足場立込
今日はちょっと早めに現場へ…
台風も通り過ぎ、心地よい秋晴れ!
プレカット工場より加工を終えた木材が届きました~。

4トントラック2台分。置き場所にも困ります。
おまけに仮設足場の立込みも重なる始末。

その指示をするための早起きでした。
大工さんが使う順番を考慮して、
木材を荷下しする場所を指示します。
道路に面する場所に置くため、
念のためにブルーシートをかけています。

着々と上棟の準備が進みます。
午後は倉庫で金物を揃えました。
明日より、現場で大工さんの作業が始まります!
台風も通り過ぎ、心地よい秋晴れ!
プレカット工場より加工を終えた木材が届きました~。

4トントラック2台分。置き場所にも困ります。
おまけに仮設足場の立込みも重なる始末。

その指示をするための早起きでした。
大工さんが使う順番を考慮して、
木材を荷下しする場所を指示します。
道路に面する場所に置くため、
念のためにブルーシートをかけています。

着々と上棟の準備が進みます。
午後は倉庫で金物を揃えました。
明日より、現場で大工さんの作業が始まります!